
【事業承継・M&A】個人事業主は事業承継できる?法人との違いはある?
個人事業主でも事業承継は可能です。
せっかく大きくした事業を廃業にするのはもったいないですよ。
親族や従業員・信頼できる人に事業を引き継いでもらえないか、情報を集めていきましょう。
そこで今回は個人事業主が事業承継をする方法や、法人との違いをまとめました。
個人事業主も事業承継できる

「事業承継は法人しかできない」と思われがちですが、実は個人事業主も可能です。
ここでは個人事業主が事業承継する3つの方法を説明します。
贈与
「贈与」とは事業用資産や負債を、生前に渡すことを言います。
特に後継者が親族である場合に選ばれる方法です。
ただし、受け取った側は高額な贈与税を支払わなければいけません。
例えば30代の子が父から1,000万円もらった場合30%の税率がかかり、贈与税額は177万円となります。
「そんなに贈与税を払うのはもったいないな…」と思えば、後継者候補が引き継ぎをためらってしまうかもしれません。
贈与税の負担を軽くする方法はいくつかあるため、早めに準備しておくことが大切です。
例えば年間110万円までなら贈与税がかからないこと(暦年課税制度)を知っていれば、何年かに分けてコツコツと贈与する計画を立てられるでしょう。
相続
「相続」とは事業者が亡くなったあとに後継者が引き継ぐことを指します。
注意点としては、遺書がないと自分の希望と異なる形で相続される恐れがある点です。
仲が良かった兄弟姉妹も、いざ資産を分けるとなるとトラブルに発展するかもしれません。
「誰に」「何を」「どのように」分けるかを、きちんと書面に残しておきましょう。
売却(M&A)
個人事業主が事業承継を考えるとき、問題となるのが後継者不足です。
親族や従業員に引き継いでもらおうとしても断られてしまうケースが多く、仕方なく廃業を選ぶ人もいます。
事業が上手くいっているなら、贈与や相続だけではなく「売却(M&A)」も検討してみましょう。
売却なら親族・従業員という縛りがなく、全国各地から候補者を探せます。
後継者問題を解決しやすく、さらに売却資金を受け取れるのが大きなメリットです。
引退するにしても新しい事業を始めるにしても余裕ができます。
【事業承継】個人事業主と法人との違い
事業承継と一言で言っても、個人事業主と法人とのケースには違いが存在します。
違いを確認した上で、準備を始めましょう。
個人事業主は株式譲渡が利用できない
法人の場合、事業承継の方法として「株式譲渡」が選べます。
経営者が保有する株式を後継者へ譲ることで経営権も移ります。
会社はそのままの形で存続するため、許認可なども引き継ぎの対象となります。
しかし個人事業主にはそもそも株式がないため、事業承継の方法として株式譲渡を利用できません。
現事業は廃業→後継者が開業という形になり、基本的に許認可はあらためて取得する必要があります。
個人事業主は廃業手続きが必要

法人の場合は経営者が変わっても会社自体は変わりません。
そのため事業承継時でも廃業手続き(解散の登記と精算)は不要です。
一方、個人事業主の場合、事業内容が同じであっても前経営者と後継者はそれぞれ別の個人という扱いになります。
例えば息子さんに引き継いでもらうケースでは、あなたは廃業手続きを、息子さんは開業手続きをする必要があります。
先代経営者は廃業手続きを行う
廃業手続きでは、以下のような書類を所轄税務署と管轄の都道府県税事務所に提出します。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 青色申告の取りやめ届出書
- 事業廃止届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
- 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
後継者は開業手続きを行う
後継者は税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を、都道府県税事務所と市町村に「事業開始等申告書」を提出します。
屋号(お店や事務所の名前)を引き継ぐ場合も、開業届の屋号欄に記入するだけで構いません。
※商号登記している屋号を使いたい場合は法務局に出向く必要があります。
屋号をそのまま使用すれば、顧客や取引先も安心できるでしょう。
個人版事業承継税制を利用すると納税が0円になる

贈与・相続を選ぶと、後継者に税金の負担がかかってしまいます。
高額な納税金額のせいで断られるケースも考えられるため、「いかに税金の負担を減らせるか」は重要なポイントです。
おすすめは「事業承継税制」の活用です。
事業承継税制とは、簡単に言うと、贈与税・相続税をゼロにできる制度です。
ただし、個人事業主が対象の「個人版事業承継税制」と法人格が対象の「法人版事業承継税制」には違いがあります。
さらに法人版事業承継税制には「一般措置」と「特例措置」が設けられており、特例措置のほうが優遇されます。
個人版事業承継税制と、法人版事業承継税制の一般措置・特例措置を比較してみましょう。
| 個人版事業承継税制 | 法人版事業承継税制 | |
|---|---|---|
| 期間 | 2028年10月31日まで | 一般措置:期限なし 特例措置:2027年10月31日まで |
| 対象 | 特定事業用資産 | 一般措置:総株式数の3分の2まで特例措置:全株式 |
| 青色申告 | 必要 | 不要 |
| 減額割合 | 100%(納税猶予) | 一般措置:贈与100%、相続80% 特例措置:100% |
| 後継者の要件 | 特定事業用資産に係る事業に従事していたこと | 後継者(および後継者と特別の関係がある者)が総議決権数の50%を超える議決権数を保有する |
対象となる資産
法人版事業承継税制では株式が対象となり、個人版事業承継税制では特定事業用資産が対象となります。
特定事業用資産とは具体的に以下のような資産です。
イ 宅地等(400平方メートルまで)
ロ 建物(床面積800平方メートルまで)
ハ ロ以外の減価償却資産で次のもの
・固定資産税の課税対象とされているもの
・自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの
・その他一定のもの(一定の貨物運送用および乗用自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産)
参考:No.4153 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除(個人版事業承継税制)|国税庁
減額される割合
法人版事業承継税制の一般措置では、要件を満たせば贈与100%・相続税80%が減額されます。
この割合でも負担は軽くなりますが、多額の資産を相続した場合、納税金額が気になるところでしょう。
しかし、個人版事業承継税制を使えば贈与・相続いずれも100%減額、つまり納税金額を0円にできます。
個人版事業承継税制を活用し、「贈与税・相続税が高いために後継者候補に断られる…」というケースを回避しましょう。
まとめ
今回は個人事業主が事業承継をする方法や、法人との違いをまとめました。
事業承継は法人向けというイメージがあるかもしれませんが、個人事業主も事業承継が可能です。
方法としては贈与・相続・売却(M&A)の3つから選べるため、早めに後継者探しを始めましょう。
事業承継における個人事業主と法人との主な違いは以下の通りです。
- 個人事業主は株式譲渡が利用できない
- 個人事業主は廃業手続きが必要
- 個人版事業承継税制を利用すると納税が0円になる
個人事業主の事業承継を学べば、育てあげた事業をスムーズに引き継いでもらえるでしょう。
アアルコンサルティングオフィス(アアル株式会社)は経営革新支援機関として、中小企業経営者の皆様に役立つ情報を発信しています。中小企業向けの補助金制度なども解説しておりますので、ぜひご覧ください。
認定支援機関をお探しの方へ
各種補助金申請、M&A・事業承継・引き継ぎ、資金調達のご相談は、アアルコンサルティングオフィス(アアル株式会社)へ。お問い合わせは下記のフォームからお願いします。
監修
執筆

アアルのアルコです。経営に関わる記事を投稿していきます。
Youtube「アアルノアルコチャンネル」もやっていますので、ぜひご覧ください。

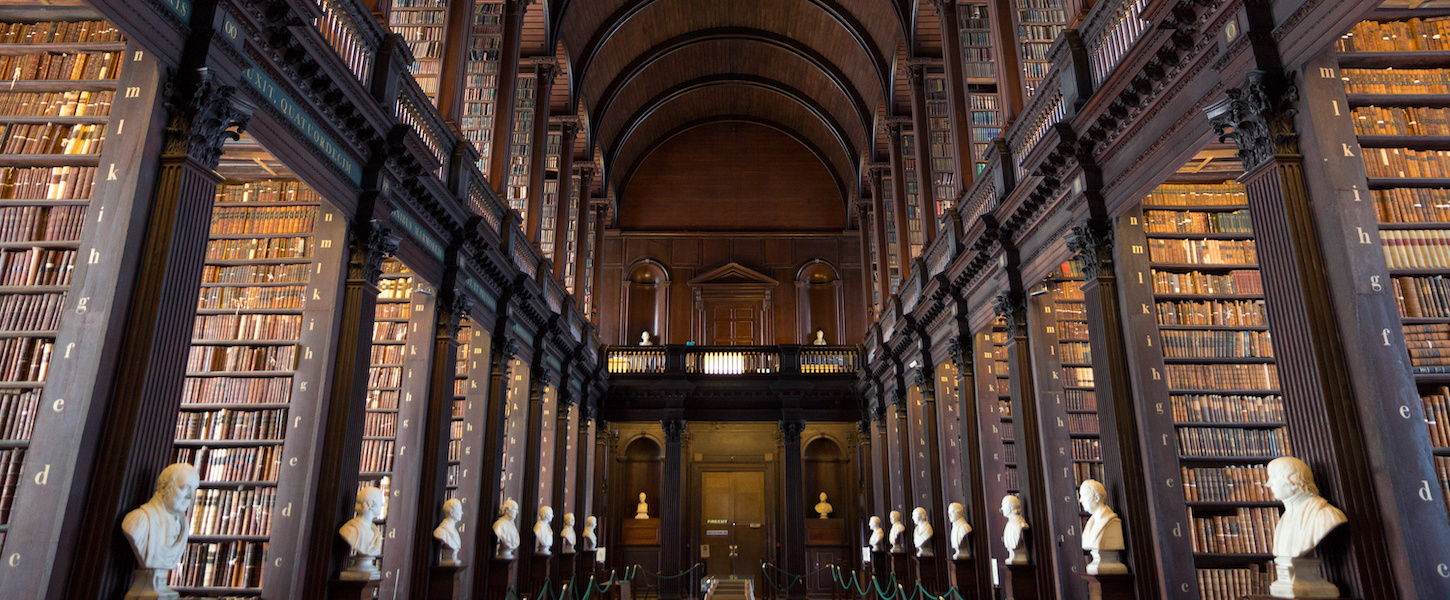







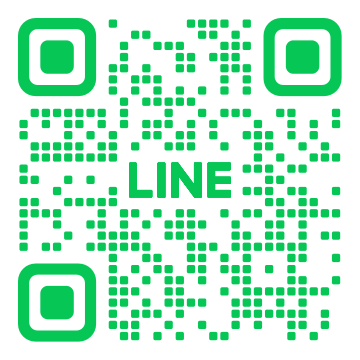

この記事へのコメントはありません。