
【経営改善計画】認定支援機関を選ぶときのポイント
目次
経営改善計画=「経営を立て直す抜本的な計画」
中小企業庁が実施する「経営改善計画策定支援」ー。この「経営改善計画」には、主に次のような特徴があります。
・困難な状況にある事業者が、経営状況を改善するための抜本的な計画である
・多くの場合、「一時的な返済ストップ」や「減額」など、金融機関への返済計画の見直しを伴う
・経営革新等認定支援機関の支援のもと作成する
「抜本的な計画」「返済計画の見直し」「経営革新等認定支援機関」というキーワードがありますが、これら3点は密接につながっています。今回は、「経営革新等認定支援機関の支援のもと作成する」という点から、この計画の特徴を解説します。
経営革新等認定支援機関とは経営計画策定のプロ
そもそも、経営革新等認定支援機関とは何でしょうか。
経営革新等認定支援機関(以下「認定支援機関」)とは、「中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)」のことをいいます(引用元「ミラサポPlus」)。
つまり認定支援機関とは、国の認定を受けた支援機関=いわば、「経営計画策定のプロ」というべき存在です。
認定支援機関は全国に38,000ある
「経営計画策定のプロ」と言っても、見つけるのが難しいわけではありません。
2024年8月現在、全国には約38,000の認定支援機関が存在し、国が運営する検索システムを使って、エリアごとに様々な条件をつけて検索することができます。
認定経営革新等支援機関検索システム
でも、これだけの数があるからこそ、どの認定支援機関を選べば良いか迷われるかもしれません。
認定支援機関は「見つけること」より「自分に合った相手に出会うこと」の方にこそ、むしろ難しさがあります。
認定支援機関を選ぶときのポイントは「事業者が主体になった対応をしているか」
冒頭で、経営改善計画は「抜本的な計画」であり「返済計画の見直しを伴う」ものだと触れました。
「厳しい現実と向き合い、経営を立て直していく」ということですが、だからこそ、認定支援機関には高い専門性と経営者自身の「強い意志」が不可欠です。
このような中で、もし認定支援機関が、自身の「専門性」だけを優先して計画を作ったらどうでしょうか?
金融機関の理解・納得は得られるかもしれません。ですが、経営者はどうでしょうか?
「損益をプラスにするためだけの実態を無視した成長率」「自身の望まない事業の方向性」ーこういったものが書かれた計画に、経営者は取り組んでいけるでしょうか?
おそらく難しいでしょう。なぜなら、そこに「こうありたい」という経営者の「想い」がないからです。そして、「想い」がないところに、強い意志は生まれません。
つまり、経営者にとって望ましいのは、「専門性」だけでなく、進むべき方向性や進んでいくためのアクションを経営者主体で考え、助言してくれる認定支援機関なのです。
この「専門性とあわせ、経営者に寄り添ってくれるかどうか」を測るためには、実際に相談してみるのが一番です。
上記の検索システムで複数の候補に絞り込んだ上で相談を申し込んだり、付き合いの深い金融機関から紹介してもらうのも良いでしょう。
まとめ
今回は、経営改善計画のもつ性質から、認定支援機関を選ぶときのポイントについて解説しました。
経営改善計画は、単なる机上の計画ではなく、実際に改善に向けて進んでいけることが重要です。
そのために、ぜひ「厳しい現実を踏まえつつ事業者に寄り添って」計画作りをサポートしてくれる認定支援機関を見つけましょう。
認定支援機関をお探しの方へ
各種補助金申請、M&A・事業承継・引き継ぎ、資金調達のご相談は、アアルコンサルティングオフィス(アアル株式会社)へ。お問い合わせは下記のフォームからお願いします。
監修
執筆

会社の長期利益獲得に向けた実行可能な事業計画を、ともに設計し、架け、渡っていく、伴走者としてご支援させて頂きます。

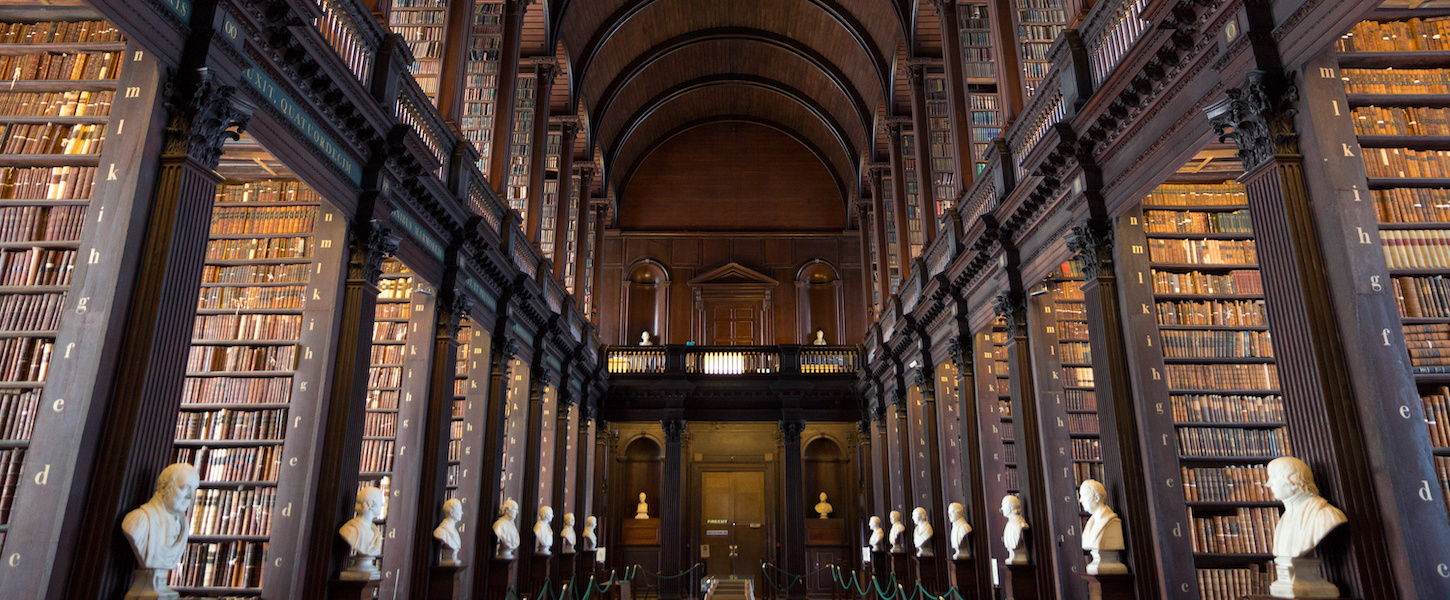



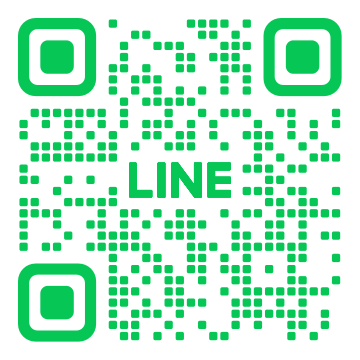

この記事へのコメントはありません。