
【事業承継・M&A】事業承継で生じる問題とは?対応策もあわせて解説!
事業承継では、思わぬトラブルが発生してしまい、失敗するケースが多く見られます。
引き継ぎ後も会社を発展させていくには綿密な準備が必要です。
そこで今回は事業承継で生じる問題と対応策をあわせて解説します。
目次
問題1.後継者が見つからない
「引退を考えているが後継者がいない」と困っていませんか?
日本政策金融公庫総合研究所の調査によると、後継者が決まっている中小企業はたったの12.5%です。
22.0%が事業承継を希望しているのに後継者が決まっていません。
その中には「子どもや妻に任せたいが了承してくれない」「ふさわしい候補がいない」なども含まれます。
あなたの会社も同じ状況なら、最終的には、後継者が決まらないせいで廃業まで追い込まれるかもしれません。
参考:中小企業の事業承継に関するインターネット調査(2019年調査)
対策1.M&Aを活用する

後継者は親族や従業員の中から探すのが主流ですが、最近はM&Aを利用する経営者も増えてきています。
M&Aマッチングでは全国から後継者を探せるため、比較的スムーズに優秀な人材が見つかります。
また、株式の売却益を得るため、引退後の生活にゆとりができるのもメリットです。
家族・社内で後継者候補がいなくとも諦めず、M&Aを検討するのが賢い選択です。
M&Aは煩雑な手続きを含むため、専門家の知識なしには実施するのは難しいかもしれません。
金融機関やM&Aを専門に扱う業者などに相談しましょう。
問題2.後継者の経営能力が不安
後継者が決まったとしても、本人の能力がまだ十分ではないケースも考えられます。
経営者としてのマインド・経営知識・リーダースキルなどが足りなければ、事業は安定しません。
また、自社の事業や業界に精通していなければ判断も誤ってしまうでしょう。
能力不足の後継者が事業を引き継けば、数年後、会社の存続が危ぶまれるかもしれません。
うまくいかずに退社、次の後継者がすぐには見つからず、前経営者が戻らなければいけなくなる可能性もあります。
対策2.早めに後継者の教育を行う

経営者に必要な能力を身につけるために、多くの企業では数年前から教育を行います。
- 現経営者が自ら指導する
- 社内で実務的な経験を積ませる
- 経営幹部として勤務させる
- 他社に勤務させる
- 研修・セミナーに参加させる
特に、社長自らが後継者に理念(ミッション・バリュー・ビジョン)を教えることは重要です。
事業承継で引き継ぐものは従業員・設備・不動産・株式など「目に見える資産」だけではありません。
事業方針・経営戦略など、企業の方向性を定める理念も大切な資産です。
これまでに大切にしてきた考え方を後継者も深く理解することで、その考えに基づいて行動できるようになります。
もしも会社の経営者が交代した途端に経営理念が変われば、従業員も混乱し、業績悪化を呼ぶかもしれません。
会社を守るために、後継者にノウハウ・知識を十分に伝え、現経営者に頼ることなく業績を伸ばせる人材へと育成していきましょう。
問題3.取引先との関係が悪化する
中小企業では社長が「会社の顔」であるケースも多いですよね。
取引先は自社の収益や事業計画に大きな影響を与える存在です。
「経営者が変わると、取引先との信頼関係が崩れてしまうのではないか」と心配する人もいるでしょう。
特にM&Aで別の会社の傘下に入った場合など、経営方針が大幅に変化すれば取引停止も考えられます。
大手取引先との契約解除が原因で、業績悪化を招くかもしれません。
対策3.早い段階から後継者を紹介しておく

これまで特に取引先とトラブルがなくとも、引き継ぎをきっかけに取引関係の見直しがされるかもしれません。
事業承継がある程度進んだら、仕入先や得意先に後継者を紹介しておきましょう。
早い段階から商談に同行させるようにすれば、信頼関係も引き継ぎできます。
特に重要な取引先については、現経営者・後継者と同席して面会するなど丁寧な対応が求められます。
問題4.贈与税・相続税が高額
会社を譲ろうと考えるとき、気になるのが贈与税・相続税です。
特に事業が伸びていて自社株の評価が高い場合、納税金額が高額になってしまいます。
支払うのは後継者ですから、「納税金額が高いから」と引き継ぎを渋るケースも考えられるでしょう。
また、納税には期限が定められています。
- 相続税:死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
- 贈与税:もらった年の翌年の2月1日から3月15日まで
短期間にお金を工面しなければならず、万が一遅れると加算税・延滞税がかかる場合があります。
資金が足りなくなり、事業継続が難しくなるケースも考えられるでしょう。
対策4.事業承継税制を活用する
「事業承継税制」は後継者の負担を軽くするために作られた制度です。
事業承継税制の条件を満たせば一時的に納税が猶予になり、最終的には免除となる可能性があります。
つまり高額の贈与税・相続税を0円にすることも可能です。
非常に複雑な制度のため、自社内で進めるのではなく税理士などのサポートを受けましょう。
他にも節税対策は考えられるため、事業承継について知識を持つ専門家に相談することをおすすめします。
問題5.個人保証のせいで引き継ぎ拒否
融資を受ける際、経営者には個人保証を求められることがあります。
事業承継を行うと、通常は、後継者も個人保証(連帯保証)を引き継ぐことになります。
しかし連帯保証人になれば、万が一会社に何かあったときに自分の財産を失う危険性があります。
「連帯保証人になりたくない=後継者になりたくない」と拒否する人も少なくないのが現状です。
対策5.経営者保証に関するガイドラインを活用する
実は、後継者に個人保証を引き継がせずに事業承継できる方法も存在します。
「経営者保証に関するガイドライン」を活用すれば、保証解除などの対象となる可能性があります。
主な要件はこちらです。
- 主債務者が中小企業であること
- 保証人が個人で、主債務者である中小企業の経営者であること
- 主債務者・保証人が弁済について誠実で、財産状況の情報開示を求められたら従うこと
- 反社会勢力でないこと
「経営者保証に関するガイドライン」の要件を満たせば、現経営者も後継者も保証なしに事業承継できる可能性が高まります。
まとめ
今回は事業承継で生じる問題と対応策をあわせて解説しました。
- 問題1.後継者が見つからない→M&Aを活用する
- 問題2.後継者の経営能力が不安→早めに後継者の教育を行う
- 問題3.取引先との関係が悪化する→早い段階から後継者を紹介しておく
- 問題4.贈与税・相続税が高額→事業承継税制を活用する
- 問題5.個人保証のせいで引き継ぎ拒否→経営者保証に関するガイドラインを活用する
事業承継は準備不足のまま進めてしまうと、大きなトラブルを引き起こします。
どのような問題が起こり得るかを知り、対策を検討しましょう。
自社内だけで進めず、知識豊富な専門家に相談することも、成功へのポイントです。
アアルコンサルティングオフィス(アアル株式会社)は経営革新支援機関として、中小企業経営者の皆様に役立つ情報を発信しています。中小企業向けの補助金制度なども解説しておりますので、ぜひご覧ください。
認定支援機関をお探しの方へ
各種補助金申請、M&A・事業承継・引き継ぎ、資金調達のご相談は、アアルコンサルティングオフィス(アアル株式会社)へ。お問い合わせは下記のフォームまたは、アアルのLINE公式アカウントからお願いします。
監修
執筆

アアルのアルコです。経営に関わる記事を投稿していきます。
Youtube「アアルノアルコチャンネル」もやっていますので、ぜひご覧ください。

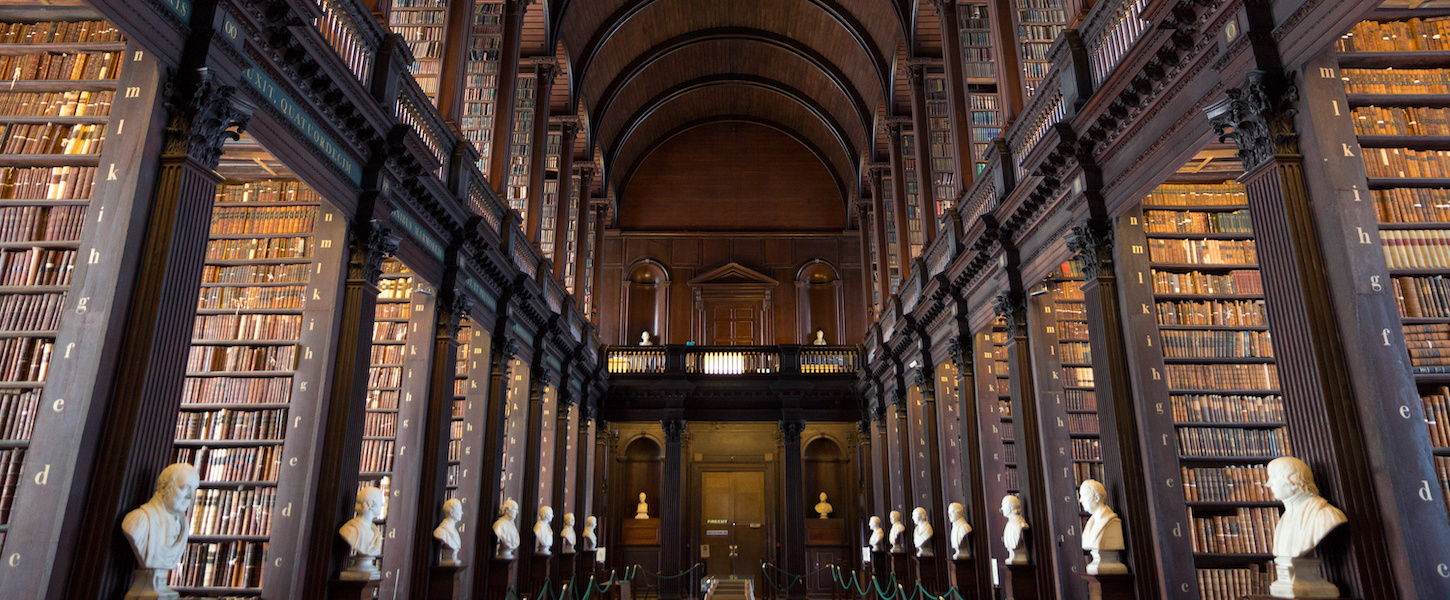









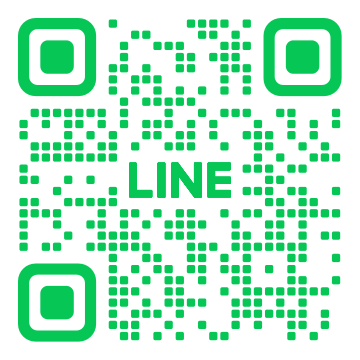

この記事へのコメントはありません。